
ベンチャー企業に最適なオフィスの種類と選び方について解説
2025.07.11
内装デザイン
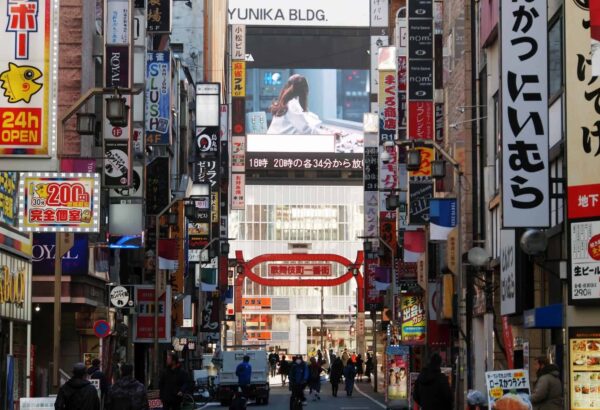
風営法と飲食店開業の関連とは?許可・規制や届出の要否を解説
2025.07.04
内装デザイン

旅館業許可とは?開業手順と必要な資格、旅館業法について解説
2025.06.27
内装デザイン
換気設備 2024.07.16
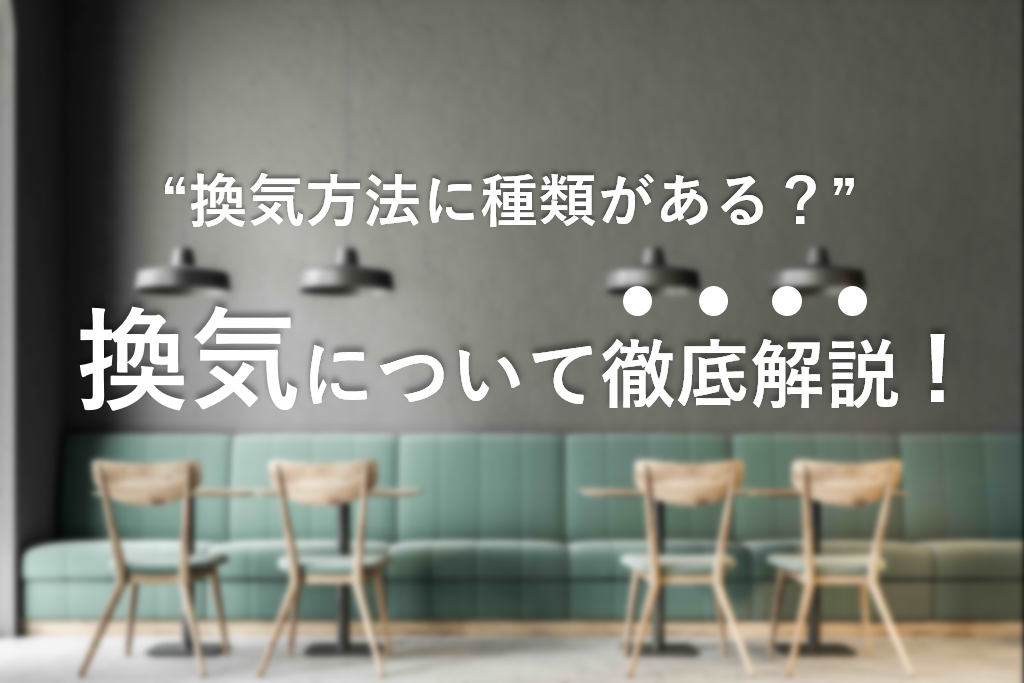
Q. 業務施設に適した換気方式の違いは?
第一種・第二種・第三種は、給気・排気の手段が異なり、それぞれの構成によって空気の流れ方や気圧バランスが変わります。業種や使用目的により適切な方式を選ぶことが重要です。
Q. 換気と省エネはどのように関係する?
換気方式の選定次第で空調負荷が変化し、エネルギー効率に大きな影響を与えます。熱交換型の換気を取り入れることで、ZEB実現に貢献できるケースもあります。
Q. 法令上、法人施設に必要な換気基準は?
建築基準法や労働安全衛生法では、室内の空気質維持のために換気設備の設置と換気量の基準が明示されています。設計時には法令への適合が必要です。
法人施設における換気設備の役割は空気の入れ替えによる快適性の確保だけでなく、従業員の健康維持、空調効率の最適化、そして法令順守といった多方面にわたります。
とりわけ「第一種換気」「第二種換気」「第三種換気」といった種類ごとの違いは、建物用途や業務内容によって選定が分かれる重要な要素です。
さらに近年では省エネ建築の目標としてZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の概念が注目されており、換気方式の選定がエネルギー削減と空調制御に与える影響も無視できません。
この記事では法人施設の設計・運用担当者を対象に換気方式の違いとその選び方、エネルギー効率との関係、法令基準との整合性を一つひとつ解説していきます。
目次

法人施設における換気方式は、「空気の流れをどう制御するか」という視点から第一種・第二種・第三種に分類されます。
ここでは、それぞれの基本構造と分類の考え方を紹介し、実務での理解を助けるベースを解説します。
換気は建物内の二酸化炭素や湿気、ホコリ、ウイルスなどを排出し、新鮮な外気を取り込むことで、室内の空気環境を健全に保つ役割を担っています。
特に法人施設では、長時間の滞在や不特定多数の出入りがあるため、換気が不十分だと空気の汚れが蓄積しやすく、従業員の体調や業務効率にも影響を及ぼします。
またウイルス感染症対策としても換気の重要性は高まっており、オフィスや商業施設、医療・介護施設では計画的かつ効果的な換気が求められています。
適切な方式を選ぶことで、空気の質を保ちながらエネルギーも節約できる可能性があるのです。
換気は大きく「自然換気」と「機械換気」に分けられます。
自然換気は、窓や通風口などから風の力や温度差を利用して空気を流す方式です。
初期コストが低く電力も不要なため一見経済的に思えますが、天候や立地条件に影響されやすく換気量を安定して確保するのが難しいという課題があります。
一方、機械換気はファンなどの機器を使って強制的に給気・排気を行います。
こちらは換気量を正確にコントロールでき、密閉性の高い建物や室温管理が必要な環境にも対応可能です。
法人施設では、基本的に機械換気方式が主流とされており、法令でもその設置が求められるケースが一般的です。
機械換気はさらに、「第一種」「第二種」「第三種」の3つに分類されます。
これは「給気」と「排気」のどちらを機械で行うかによって分けられます。
この分類により、空気の流れ方・気圧バランス・空気質の制御性に違いが生まれます。
第一種換気は給気・排気の両方を機械で制御する方式であり、法人施設における空気管理の精度を高めるうえで非常に有効です。
ここではその仕組みや特徴、導入の際に考慮すべき実務上のポイントを解説します。
第一種換気では、ファンを用いて外気を取り入れると同時に室内の汚れた空気を強制的に排出します。
この際に「全熱交換器(熱交換換気ユニット)」を使えば、外気と内気の温度・湿度を一定範囲で調整できるため外気温との差による冷暖房負荷を軽減できます。
たとえば冬場に5℃の外気をそのまま室内に入れると、空調コストが大きくなりますが、全熱交換器を通すことで20℃前後に調整された空気を取り入れられます。
このように、第一種換気は空気質の管理と省エネの両立が可能なシステムといえます。
第一種換気は、空気の流入・流出を厳密に管理できるため、特に高い衛生環境や空調管理が求められる施設での導入が進んでいます。
たとえば以下のような施設が代表的です。
これらの施設では、外気の浄化、室内圧力の調整、温度・湿度の安定化といった複合的な制御が求められます。
第一種換気はそれらを一括で管理できるという点で非常に優れています。
第一種換気は構造が複雑であり給排気の両方に機械設備が必要となるため、導入の際は設置スペースや電源系統への配慮が求められます。
また、定期的なフィルター交換や機器メンテナンスも欠かせません。
一方で省エネ性の高い熱交換ユニットを併用することで、空調の消費エネルギーを削減できる可能性もあります。
長期運用を前提とする法人施設では、単なる導入のしやすさだけでなく、維持管理と省エネ効果のバランスを考慮することが重要です。
第二種換気は、外気の供給を機械で行い、排気は自然に任せる方式です。
室内の気圧を「陽圧」に保つことができるため、特定の業種において衛生面で大きなメリットがあります。
ここでは、その活用例や構造上の注意点を紹介します。
第二種換気の最大の特徴は室内を外気よりも高い気圧状態にできる点です。これにより、外部からの埃や虫、菌などの侵入を抑制する効果が期待されます。
つまり、「中から押し出す」形で空気を管理するため、異物混入を嫌う施設には非常に適している換気方式といえるでしょう。
ただし、排気が自然換気となるため、外部条件(風圧、気温差)に影響されやすく、排気効率が不安定になるリスクもあります。
第二種換気は、クリーンルームを必要とする環境に多く導入されています。
以下のような業種・施設でよく採用されているのが特徴です。
これらの現場では、外部からの汚染物質をできる限り遮断し、清浄な空気を保つことが衛生管理の基本となります。
そのため、第二種換気による陽圧管理は非常に有効な手段となっています。
第二種換気は室内の気圧を上げるため、隣接空間への空気の流れが起きやすくなります。
そのため、施設内のゾーニングや気流設計が必要不可欠です。たとえば、清潔区域から準清潔区域への一方通行の空気の流れを作るなど、空調設計とセットで導入する必要があります。
また空気がこもりやすいという課題もあるため、自然排気口の配置や定期的な環境測定も併せて実施することが望ましいです。
第三種換気は排気を機械で行い、給気は自然に任せる方式です。
シンプルな構成で初期導入のハードルが低いため、多くの法人施設や中小規模の建物で採用されています。ここではその特徴と注意点を整理します。
第三種換気では、壁や窓などに設けた吸気口から自然に外気を取り入れ、天井や壁に設置したファンで室内の空気を排出します。
これにより、室内は「負圧(外気より低い気圧)」となり、空気の流れが生まれます。
機械排気は常に一定量の空気を排出できるため、シンプルながらも確実な換気効果が得られるのが特徴です。
一方で、自然給気に頼る部分は気候や外気圧に影響されるため、吸気が不安定になりやすいという点には注意が必要です。
第三種換気は以下のような法人施設で多く導入されています。
これらの施設では、「高精度な空気制御」よりも「最低限の空気の入れ替え」が求められるため、第三種換気の簡易性が適しているといえます。
特に短時間の滞在や人数の少ない空間においては、十分な機能を発揮します。
第三種換気は自然吸気に依存するため、外壁に設置される吸気口の位置や建物の気密性が換気性能に大きく影響します。
たとえば、吸気口が風の通らない場所にあると空気が入りにくく、排気ファンだけが稼働して負圧が強くなりすぎることがあります。
また、冬場など寒気が直接室内に入ることで、室温が下がるケースもあるため、断熱設計との併用や吸気口へのフィルター装備など、環境に応じた対策が求められます。

法人施設における換気方式の選定は、業種ごとに求められる衛生環境・気流制御・空気質の管理レベルが異なるため一律の判断では不十分です。
ここでは主要な業種を例に、それぞれに適した換気方式の方向性を紹介します。
医療施設や高齢者向け介護施設では、空気感染対策と清潔区域の確保が極めて重要です。
たとえば、病室や診察室ではウイルスや菌の拡散を防ぐ必要があり、特に感染症病棟では陽圧・陰圧の管理も考慮されます。
このような環境では、第一種換気方式が適しています。機械的な給気・排気を使って空気の流れを完全にコントロールできるため、室内の空気質を安定的に維持できます。
また、手術室や無菌室など一部のゾーンでは第二種換気で外気の流入防止(陽圧)を図るケースもあります。
食品加工や製造ライン、飲食店の厨房などでは蒸気や油煙、粉じんなどの発生が避けられず、迅速かつ大量の排気が求められます。
こうした環境では、第三種換気方式が適しています。
自然給気と機械排気によって、排気を主導的に行えるため発熱・発湿による作業環境の悪化を防ぐことが可能です。
ただし、気密性の高い空間では給気量の確保に工夫が必要となるため、設計段階での吸気口の配置が鍵を握ります。
オフィス空間では、従業員が長時間滞在することから、CO₂濃度の管理や空気のこもり防止が求められます。
また、省エネ性能や快適性も重要な判断軸になります。
このようなケースでは、第一種換気方式+全熱交換器の組み合わせが最も効果的です。
外気導入による温度ロスを抑えながら、一定の換気量を安定的に確保できるため、空調負荷の軽減と室内空気環境の向上が両立できます。

ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の達成には、照明や空調だけでなく、「換気」も重要な構成要素です。
ここでは、換気設備がZEBにどのように貢献するか、またエネルギー効率向上の観点からの最適化ポイントを解説します。
ZEBとは、「建物で消費する一次エネルギー量を、再生可能エネルギーなどで相殺し、年間のエネルギー収支をゼロにする建築物」を指します。
近年、企業のESG対応やカーボンニュートラルの流れを受けて、オフィスビル・教育施設・庁舎など法人施設でもZEB化への取り組みが加速しています。
換気はZEB評価項目のひとつであり、空調と連携しながら効率的なシステム設計を行うことが求められます。
ZEBを目指す上で、第一種換気における全熱交換器の活用は非常に効果的です。
外気を取り入れる際に、排気側の熱エネルギーを回収してプレヒート/プレクールすることで、空調設備の消費エネルギーを大幅に削減できます。
たとえば、外気温が5℃の冬季でも排気側の暖かい空気(20℃)を利用して外気を15℃程度にしてから室内に取り入れることができれば、暖房の稼働量は大きく減ります。
このように、換気と空調の連携こそがZEB設計の鍵を握っています。
ZEB達成において、エネルギー削減項目は大きく「照明」「空調」「換気」「給湯」に分けられます。
このうち、空調・換気は施設全体のエネルギー消費量の約4〜5割を占めるため、設計初期段階から一体的に検討すべき分野です。
具体的には以下のような施策が有効です。
これらを通じて、「必要なときに、必要な分だけ換気する」という運用に切り替えることで、無駄な消費電力を削減しつつ、快適性を損なわない室内環境が実現できます。
法人施設で換気設備を設置・運用するにあたっては、建築基準法および労働安全衛生法による規定を正しく理解しておくことが必要です。
ここでは換気に関する代表的な法的基準と、設計・管理時の留意点について解説します。
建築基準法では、建物の用途や面積に応じて必要な換気量が定められています。
たとえば、「居室」では1人あたり毎時30立方メートル(30m³/h・人)以上の換気量を確保することが義務づけられており、その手段として自然換気または機械換気設備の設置が求められます。
また、建築確認申請時には、換気方式の図面および必要換気量を満たすことを証明する計算書の提出が必要となるケースもあります。
特に密閉性の高い建物では機械換気の導入が実質的に必須となるため、設計初期から設備計画に組み込むことが重要です。
労働安全衛生法では、「事務所衛生基準規則」において、労働者が従事する室内環境の空気質を明確に定義しています。
そのなかでCO₂(二酸化炭素)の濃度については、1,000ppm以下に保つことが望ましい基準とされています。
この基準を満たすためには、適切な換気回数の確保だけでなく、二酸化炭素センサー(CO₂モニター)による実測管理も効果的です。
オフィスビルや学校などの施設では、長時間滞在する空間であるため、CO₂濃度が換気の必要性を示す指標として重視されています。
換気方式の選定および導入に際しては、以下の法的確認事項をチェックしておくと安心です。
これらは設計士や設備業者とのやりとりのなかで確認し、計画段階から明確に反映させることで、法令違反や後戻り工事を防ぐことができます。
換気方式を現実的に選ぶ場面では、法令や仕組みだけでなく、自社施設の条件や運用スタイルに合った選定が求められます。
ここでは、実務の現場で活用できる判断項目をリスト形式で整理します。
まず前提として、その空間が「何のために」「誰が」「どのくらいの時間」使う場所なのかを明確にします。
たとえば以下のような分類が考えられます。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 用途 | 会議室/診察室/厨房/研究所など |
| 利用人数 | 常時数名/不特定多数/大人数 |
| 滞在時間 | 短時間滞在(15分以内)/長時間勤務 |
この3点を把握することで、必要な換気量や方式の方向性が見えてきます。
換気と空調は一体で考える必要があります。
給排気による温度ロスや湿度の変化、騒音の発生などを想定し設計段階で次の点をチェックしましょう。
これらは導入後の快適性・維持管理のしやすさに直結する要素です。
最後に換気設備は設計・施工・運用の三者が連携することではじめて効果を発揮します。
設計者や業者との打ち合わせでは、以下のような情報を事前に共有しておくとスムーズです。
このような実務視点での条件整理が、無駄のない換気設備選定を支える土台となります。
第一種・第二種・第三種の違いを一度に覚えるのは難しいと感じる方も多いでしょう。
ここでは、施設担当者や現場職員の教育・研修にも使いやすい、シンプルで実践的な覚え方を紹介します。
3つの方式の違いは、以下のように給気と排気の「どちらを機械で行うか」によって整理できます。
| 換気方式 | 給気 | 排気 | 排気 |
|---|---|---|---|
| 第一種 | 機械 | 機械 | 精密制御・全熱交換が可能 |
| 第二種 | 機械 | 自然 | 陽圧管理・外気遮断向き |
| 第三種 | 自然 | 機械 | 簡易的・導入しやすい |
この表を用いれば、新入社員や現場作業員向けにも簡単に説明でき、混乱を防げます。
研修資料やマニュアルに取り入れる際は、「施設の例と換気方式」をセットで示すのがおすすめです。以下はその一例です。
| 業種/施設 | 適した換気方式 | 理由 |
|---|---|---|
| 病院・研究室 | 第一種/第二種 | 空気の質・気圧管理が必要 |
| 飲食店・厨房 | 第三種 | 排気重視・コスト抑制 |
| オフィス・学校 | 第一種 | 快適性・空調連携が必要 |
このように実例と結びつけることで、理解と記憶の定着が早くなります。
以下のような語呂合わせや覚え方も、社内共有用に有効です。
図で表す際は青矢印で給気、赤矢印で排気を描くと直感的に伝わりやすく、資料化にも便利です。
法人施設で換気設備の導入や見直しを検討する際に、担当者から寄せられることが多い代表的な疑問について、実務的な観点から回答します。
ZEB化を目指す施設では、第一種換気+熱交換器の組み合わせが最も効果的です。
外気の熱を回収し、空調の負荷を下げながら安定的な換気を実現できるため、エネルギー削減と快適性を両立しやすくなります。また、CO₂センサーと連動した需要制御換気(DCV)もZEB達成には有効です。
労働安全衛生法に基づく「事務所衛生基準規則」では、CO₂濃度が1,000ppm以下であることが望ましいとされています。
これはおおよそ、1人あたり30m³/hの換気量を確保することに相当します。
人数や空間の大きさに応じた計算が必要で、施設ごとに適正な換気計画を立てることが求められます。
はい、既存施設でも換気方式の見直しや改修は可能です。
ただし、天井裏のダクトスペースや壁面への穴あけ制約、建物の気密性の状況などによって導入可能な方式が限られる場合があります。
まずは現状設備の確認と、外気の流入経路・排気経路を整理することが重要です。
点検や報告は、建築基準法や消防法、労働安全衛生法などの観点から一部義務付けられている場合があります。
たとえば、特定建築物では年1回の定期報告が必要になるケースや厨房排気設備では防火ダンパーの点検義務がある場合もあります。
施設の種別と用途に応じて、所轄の建築行政・保健所などに確認するのが確実です。
換気と空調は密接に関係しており、切り離して設計・運用することは適切ではありません。
換気によって取り入れた外気が空調負荷となるため、換気量が多いほど冷暖房のエネルギーも必要になります。
そのため、設計段階から両者を一体的に計画し、熱交換換気やDCV制御の導入などを通じてトータルで最適化することが推奨されます。
法人施設における換気方式の選定は、空気質の維持だけでなく、エネルギー効率や法令遵守にも深く関わる重要な要素です。
第一種・第二種・第三種換気にはそれぞれ特徴があり、施設の用途や運用環境に応じた適切な導入が求められます。
とくにZEBや省エネへの関心が高まる中で、換気は空調・照明と並ぶ「建物の消費電力を左右する要素」として注目されています。
熱交換器の活用やCO₂濃度に応じた制御システムの導入により、快適性とエネルギー最適化の両立が可能です。
換気設備の更新や新設を検討される場合は、施設の構造や利用状況を整理し、設計者や設備業者と連携しながら進めることが重要です。
この記事を参考に、より快適かつ効率的な換気環境の実現に向けた第一歩を踏み出してください。
換気設備や換気については、ReAirへお気軽にご相談ください。

2025.07.11
内装デザイン
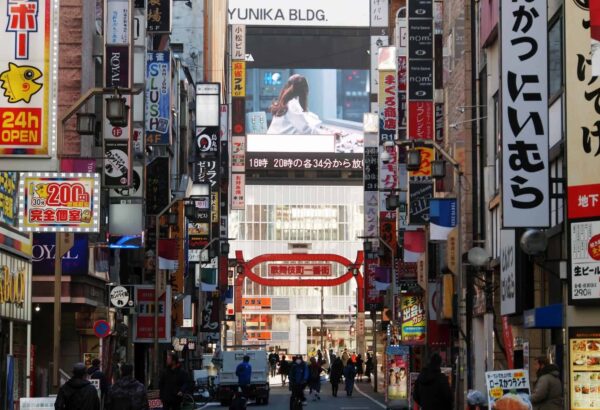
2025.07.04
内装デザイン

2025.06.27
内装デザイン