
店舗を建築・建設したい方のためのガイドライン
2026.01.30
建築・建設

ハイパースケールデータセンターの高発熱・高密度化に対応する空調設備について解説
2026.01.28
換気設備

ブックカフェの内装を作る方法は?設計内容や施工、コンセプトについて解説
2026.01.23
内装デザイン
換気設備 2024.10.27
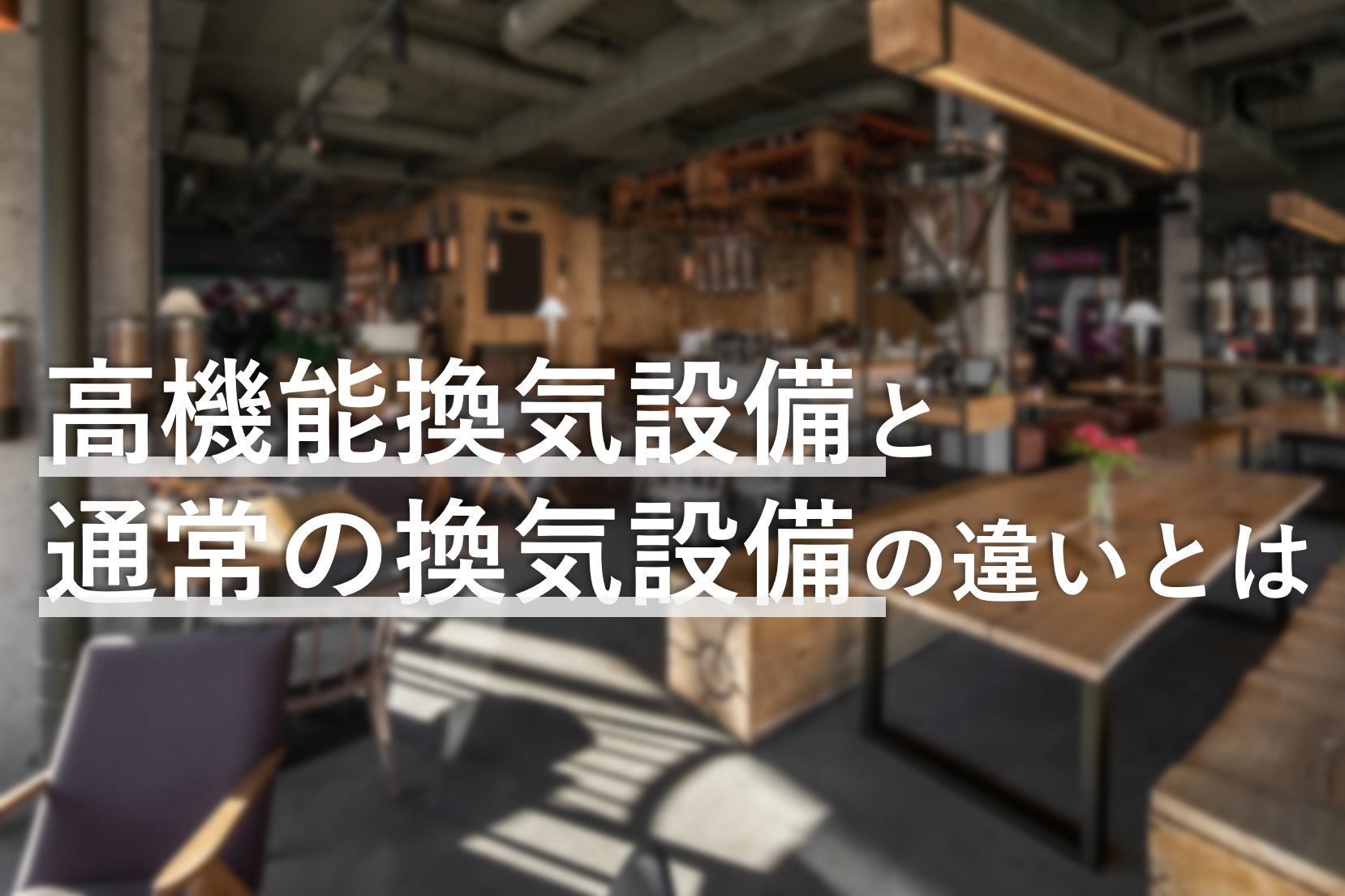
近年、建物内の「空気の質」に対する関心が高まっています。
とくにウイルス対策や省エネの観点から、従来の換気扇だけでは不十分と感じる人が増えており、「高機能換気設備」という言葉を耳にする機会も増えました。
しかし「高機能換気設備」と聞いても、何がどのように優れているのかが分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、高機能換気設備の基本から一般的な換気設備との違い、代表的な製品や換気方式、法律的な基準までを網羅的にわかりやすく解説します。
雨の日に窓を開けて換気してもいい?湿気対策をしながら換気する方法を紹介
目次

高機能換気設備とは、従来の換気扇とは異なり、「効率的な空気の入れ替え」と「室内環境の快適さ」を両立するための先進的な換気システムです。
ここでは、その特徴と一般的な設備との違いを見ていきましょう。
高機能換気設備の最大の特徴は、「省エネ性」「快適性」「清浄性」の3つを同時に実現できることです。
たとえば、全熱交換型の換気装置では、室内から出ていく空気の熱を回収し、取り込む新しい空気に熱を移します。
高機能換気設備には熱交換システム(全熱交換機)が搭載されているため、室内の温度を一定に保ちながら換気ができますので空調効率を下げることもありません。
夏は室内の冷えた空気を利用して入ってくる外気を冷やし、冬であれば暖まった室内の空気を利用して冷たい外気を暖めてから室内に入れるという仕組みになっています。
そして、熱交換は、室内の冷たい(暖かい)空気を排気する際に給気する空気に移して行われます。
このときに「きれいな空気と汚れた空気が混ざってしまうのではないか」と思われるかもしれませんが、熱交換システムでは空気を混ぜ合わせて熱交換を行うのではなく給気と排気の通り道が分かれており熱だけを交換するようになっています。
そのため、室内には新鮮な空気が供給され、汚れた空気は外に排出されますので安心してご利用いただくことができます。
これにより、外気の冷たさや暑さを室内にそのまま持ち込まずに済み、冷暖房の効率が落ちにくくなるのです。
さらに、花粉やPM2.5をフィルターで除去する機能を備えた機種も多く、外気の質が悪い地域でも安心して換気が可能です。
住宅だけでなく、病院・保育園・オフィスなど、空気の質が求められる場所でも積極的に導入されています。
一般的な換気設備といえば、キッチンやトイレに設置されている「排気専用の換気扇」が代表的です。
これらは室内の空気を外へ排出するだけの機能しか持たず、新鮮な空気は自然に任せて入ってくる形になります。
一方、高機能換気設備は「機械的に給気と排気を同時に行う」点で大きく異なります。
給排気のバランスが取れていることで、室内の気圧が安定し、ドアが開きにくくなる、隙間風が入るといった現象も軽減されます。
また、一般換気では換気量の制御が難しい一方で、高機能設備ではセンサー制御によりCO₂濃度や湿度に応じて自動で換気量を調整するモデルもあります。
換気を行う主な理由としては「湿気」や「匂い」「ホコリ」などを外に出すために行ないますが、そもそも換気の定義とは何でしょうか。
換気とは、室内の空気を室外に排出し、室外の新鮮な空気を室内に入れること。つまり室内と室外の空気を循環させ、室内の汚れた空気や匂いを外に逃すことを目的としています。
ではなぜ換気をするのかについてですが、大きく分けて3つの理由があります。
それぞれ以下に詳しく解説します。
換気の必要性と必要な換気量を解説!店舗やオフィスへおすすめな高機能換気設備もご紹介!
二酸化炭素は人間の呼吸やガスファンヒーターなどの暖房機器などの家電製品、自動車から排出されます。
この二酸化炭素は空気中に漂い残るため、換気していない場合は室内に留まり二酸化炭素濃度が増します。
室内の二酸化炭素濃度が高まることで、人体の健康に悪影響を及ぼし、
上記のように様々な症状を発症させるリスクを高めます。
さらに、室内の二酸化炭素濃度が7%以上になると意識障害を起こし、意識の消失や失神してしまう場合もあります。
また換気をしない場合、二酸化炭素濃度の上昇だけではなく、一酸化炭素や窒素、ホコリや花粉、ダニを含むハウスダストなどの汚れた空気も停滞してしまいますので、シックハウス症候群の発症リスクも高めてしまうかもしれません。
二酸化炭素濃度が上昇してしまう主な原因は、
以上のことが考えられます。
2000年初頭頃にシックハウス症候群が社会問題になり、2003年7月から建築基準法に基づくシックハウス法が施行されて以降、24時間換気設備の設置が義務となっています。
この24時間換気設備が止まっていると、気密性の高い室内では二酸化炭素などの汚れた空気が滞留するため、二酸化炭素濃度が上昇します。
24時間換気設備がある場合は常に稼働させておきましょう。
先ほどは「室内の気密性が高いと空気が滞留する」と解説しましたが、換気をする場合は逆に気密性の低い室内の場合は空気が停留してしまい、しっかり換気できない場合があります。
日本住環境株式会社様で掲載されている下図のように、機密性の低い室内で換気をした場合は所々の隙間から空気が抜けてしまいますので、効率良く換気がしにくい状態になってしまします。
ストーブなどのファンヒーターを利用することでも室内の二酸化炭素濃度を高める理由になります。
ガスや灯油を利用するストーブやファンヒーターは、燃焼させる際に二酸化炭素を発生させます。そのためストーブなどのファンヒーターを長時間稼働させることで二酸化炭素濃度を高める原因となります。
またストーブなどは二酸化炭素以外にも一酸化炭素も発生します。また一酸化炭素は無味無臭で毒性の高い気体であるため、必ず定期的な換気をするように心がけましょう。
一酸化炭素濃度が高まると『一酸化炭素中毒』になる可能性を高め、最悪の場合は命を落とすこともありますので、必ず1時間に1回など定期的に換気しましょう。
室内に大人数が多く集まると当然、二酸化炭素濃度は高まります。人間が吐く息の3~4%が二酸化炭素と言われています。全体の比率としては低いですが、人が多ければ排出される二酸化炭素の量も高まります。
室内の広さにもよりますが、人が多く集まる場所では必然的に二酸化炭素が増えますので常に換気をする、または換気の頻度を高めるなどをする必要があります。
シックハウス症候群とは、
住宅の高気密化などが進むに従って、建材等から発生する化学物質などによる室内空気汚染等と、それによる健康影響が指摘され、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
引用元:シックハウス対策のページ
シックハウス症候群の症状は、
シックハウス症候群を予防するためには、定期的な換気が欠かせません。
また換気の他には『ダニやカビの対策』『化学物質の対策』の2つが特に重要です。
カビやダニが発生する原因は主に「ほこり」と「湿気」です。
カビは湿気の多い箇所や湿気が滞留しやすい箇所に発生しやすく、特に室温が20℃以上の場合は特にカビが発生しやすくなります。
またチリやホコリなどが溜まりやすい場所にはカビと同様にダニも発生しやすくなります。
これらの対策方法は換気や掃除を定期的に行い、清潔に保つことが重要です。
特に換気は1日1回とかではなく、1時間に1回など換気頻度を高めることにより効果的に対策することができます。
すでに建築されている建物場合は換気の頻度を高める、もしくは24時間換気設備を設置する、稼働させることで対策することが可能です。
建築前の建物であれば、建設の際に利用される塗料や接着剤、防腐剤などの化学物質を控える、抑えるように相談することもできます。
現代では、特にシックハウス症候群の問題は国を上げて警鐘されているため大きな不安になるようなことはないかと思いますが、昨今の建物は機密性が高く空気が滞留しやすい作りなので、換気は常に意識しましょう。
カビは先述したように、湿度が70%以上で室温が20℃以上の環境が非常に増殖しやすく、カビが発生しやすい条件となります。
そのため、できるだけ湿度が70%以下になるように対策をする必要がありますが、湿度を下げる方法は以下が効果的です。
【シックハウス症候群】対策方法と換気不足が招く人体への悪影響とは?
全熱交換器は、高機能換気設備の中心的な技術の一つです。
ここでは、その基本的な仕組みと得られる効果について詳しく説明します。
全熱交換器は、室内から排出する空気の「熱(温度)」と「湿度」を回収し、外気と入れ替える際にその熱を移すことで、エネルギーロスを抑える仕組みになっています。
たとえば、冬場に外気温が0℃でも、室内の排気(たとえば20℃)の熱を使って新鮮な空気を15〜18℃程度に温めてから室内に取り込むことができます。
これにより、暖房で一度温めた空気の熱を無駄にせず、結果的に光熱費の削減につながるのです。
また、湿度も一緒に交換されるため、加湿器の負担が減り、乾燥を抑えた快適な空間づくりにも貢献します。
夏場には逆に室内の冷気を使って外気を冷やすことも可能です。
さらに、フィルターを通すことで花粉やPM2.5などの微粒子を除去できるため、換気と同時に空気清浄の効果も得られるのが魅力です。
2003年の建築基準法改正により、住宅においては原則として「24時間換気システム」の設置が義務付けられています。
これは、シックハウス症候群などの健康被害を防ぐための措置として導入されたもので、一定量の換気を常に維持することが求められます。
高機能換気設備は、この24時間換気の基準を満たしつつ、さらに熱交換や空気清浄などの機能を付加している点で、より高性能な仕組みだと言えます。
つまり、24時間換気は「最低限の換気性能」であるのに対し、高機能換気は「快適性と効率を追求した換気」と言えるでしょう。
たとえば、ロスナイやベンティエールのような製品は、24時間連続運転が可能でありながら省エネ運転モードや自動停止モードなども備えており、家庭にも施設にも柔軟に対応できます。
近年、高機能換気設備が注目される背景には、空気の「質」に対する関心の高まりと、法規制や社会情勢の変化があります。
ここでは、その背景と現場でよく見られる課題について掘り下げていきます。
新型コロナウイルスの感染拡大以降、「空気の入れ替え」はウイルス対策の一環として広く認知されるようになりました。
また、花粉・PM2.5・黄砂などの影響により、「空気がきれいなこと」そのものが暮らしの質を左右する要素になりつつあります。
その結果、「ただ外の空気を入れればよい」という時代から、「快適で安全な空気を管理して取り入れる」ことが求められる時代へと移行しているのです。
一方で、実際の住宅や施設では以下のような課題が多く見られます。
こうした問題は、従来の自然換気や簡易的な換気扇では対応が難しいことが多く、より高度な設備が求められる場面が増えています。
高機能換気設備は、これらの問題を一度に解消する手段として注目されているのです。
建築物における換気方法には、大きく分けて「自然換気」と「機械換気」の2種類があり、それぞれに特徴や適用条件があります。
ここでは、それぞれの基本構造と、選定時の注意点について解説します。
自然換気とは、風の力や温度差による空気の流れ(=通風)を利用して、室内の空気を入れ替える方法です。
一般住宅では、窓を開けて風を通す方法が最も典型的な自然換気です。
この方法は、電力を必要とせず、構造もシンプルなため初期コストがかからないという利点があります。
また、日中や中間期(春や秋)には、外気を心地よく取り入れられる点も魅力です。
ただし、外気温が極端に低い日や、そもそも窓を開けにくい環境(都市部の騒音・防犯対策など)では実効性に欠け、換気量の調整が難しく、花粉・PM2.5などの外気汚染物質を直接取り込んでしまうリスクもあるため、安定した室内環境を維持するには限界があります。
機械換気とは、ファン(送風機)を使って強制的に空気を出し入れする方式のことを指します。
住宅・施設においては、以下の3つの方式に分類されるのが一般的です。
最も高度な換気方式で、換気量・方向・空気の質を精密に制御できます。
全熱交換器を組み込むことで、省エネかつ快適な空間を実現できる点が最大のメリットです。
主にクリーンルームや病院など、室内を加圧して外部からの異物混入を防ぎたい場所で使われます。
一般家庭やオフィスではあまり採用されません。
一般住宅に多く見られる方式で、コストが低く施工も簡単です。
ただし、外気温の影響を受けやすく、給気側の管理が難しいため、寒冷地などでは断熱性や気密性とのバランスに配慮が必要です。
このように、用途や立地条件によって最適な換気方式は異なります。
たとえば、小さなオフィスであれば第3種換気でも十分な場合がありますが、感染症対策や冷暖房効率を重視するなら第1種が推奨されます。
高機能換気設備を導入する際には、見た目や機能性だけでなく、法令で定められた基準に適合しているかどうかを確認することが重要です。
この章では、建築基準法に基づく要件や計算方法、点検義務について解説します。
日本の建築基準法では、居室(人が常時滞在する場所)には一定の換気性能が求められます。
具体的には、1時間あたりの空気の入れ替え回数が「0.5回以上」であることが基準とされています(建築基準法施行令 第20条の9)。
この基準に適合する設備として、2003年以降の新築住宅には24時間換気システムの設置が義務づけられています。
つまり、単に「換気できる」だけでなく、「常に一定量を安定して換気できる」ことが法的にも求められているのです。
高機能換気設備は、この基準を満たした上で、さらに熱交換やフィルター機能などを追加した高性能型に位置付けられます。
換気設備を設計する際には、「部屋の広さ」や「用途」に応じて必要な換気量(=風量)を計算する必要があります。基本的な計算式は以下のとおりです。
◾️計算式必要風量(㎥/h)= 床面積 × 天井高 × 必要換気回数
16㎡ × 2.4m × 0.5回 = 19.2㎥/h
このように計算することで、使用すべき換気設備の能力を具体的に導き出せます。
現場の設計担当者や建築士がこの計算をもとに機器の選定を行います。
建物に設置された換気設備は、法律上「設置すること」だけでなく「維持管理すること」も求められています。
とくに業務用施設や共同住宅では、定期的な清掃や動作確認が必要です。
高機能換気設備では、フィルター交換の目安(3〜6か月に1回)やダクト内の点検(1年に1回程度)を忘れずに実施することで、性能を長期間維持できます。
一例として、フィルターが詰まった状態で運転を続けると、風量が低下し換気不足になるだけでなく、機器の故障リスクも高まるため注意が必要です。
高機能換気設備を導入する際、多くの方が直面するのが「どのメーカーの製品を選べばよいか」という問題です。
この章では、代表的な製品であるロスナイとベンティエールの違いを中心に、選定時の比較ポイントや導入コストの考え方、法人施設における選定事例を紹介します。
まず、ロスナイ(三菱電機)とベンティエール(ダイキン)は、どちらも日本の大手メーカーが展開する全熱交換型換気システムです。
両者の共通点は「高い省エネ性」「フィルター性能」「熱交換効率の高さ」などですが、設計思想や細かな機能には違いがあります。
| 比較項目 | ロスナイ(三菱) | ベンティエール(ダイキン) |
|---|---|---|
| フィルター性能 | 花粉・PM2.5対応モデルあり | 高性能HEPA相当フィルター搭載機種あり |
| サイズ展開 | 壁掛型・天井埋込型多数 | 床置型・天井吊り型など多様 |
| 静音性 | 静音設計モデルが多い | 商業施設向けに静音性を考慮 |
| 連携機能 | 空調機との連動可能 | スマート家電連携に強みあり |
たとえば、ロスナイはコンパクトで設置場所を選ばず、一般家庭のリフォームでも使いやすい点が特長です。
一方で、ベンティエールは広い空間や業務施設向けの高風量モデルが豊富で、建築規模に応じた設計が可能です。
高機能換気設備は高額というイメージがありますが、長期的に見れば光熱費の削減や清掃コストの低減につながる可能性があります。
| コスト項目 | 通常換気扇 | 高機能換気設備 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 1万円〜 | 10万円〜 |
| 設置工事費 | 3万円〜 | 15万円〜 |
| 年間電気代 | 約2,000円〜 | 約4,000〜8,000円 |
| フィルター交換 | 不要または年1回 | 半年に1回程度(数千円) |
このように、初期投資は高くても、省エネ設計により冷暖房費を抑えることで、5年〜10年単位で見れば総コストに差が出るケースもあります。
とくに法人施設では、設備投資に対するランニングコストの最適化が求められるため、運用費用も含めたシミュレーションが不可欠です。
法人施設では、以下のような観点から設備選定が行われます。
・建物の広さや天井高に応じた風量確保
・使用目的(オフィス・クリニック・厨房など)に応じた機種選定
・静音性・デザイン性のバランス
・メンテナンス性と部品の入手性
たとえば、小規模クリニックでは、待合室にロスナイの壁掛型を導入し、施術室にはベンティエールの高性能モデルを使うといった“使い分け”も見られます。
また、複数台の連動運転やスマート管理機能を活用することで、業務効率も向上します。
高機能換気設備は「どのような場所に適しているのか?」という疑問を持つ読者に向けて、ここでは導入に適した代表的な施設例とその理由を解説します。
オフィスや小売店舗では、空気環境の質が従業員の集中力や顧客の滞在時間に大きく影響します。
たとえば、ある事務所ではロスナイ導入後、CO₂濃度の上昇が抑えられ、従業員の「眠気」や「集中力の低下」が減少したという結果も出ています。
また、飲食店では、空気の循環によってニオイがこもりにくくなることで、客席の快適性が大きく向上します。
住宅における導入タイミングとしては、リフォーム時が最も適しています。
とくに以下のような条件が当てはまる家庭では、検討の価値があります。
高機能換気設備を取り入れることで、快適性と健康面の両方を改善することが可能です。
室内に穴を開ける施工が必要なため、計画段階での業者との打ち合わせが重要になります。
病院や高齢者施設では、空気の「清浄度」が安全性に直結します。
インフルエンザやコロナなどの感染症対策としても、常に新鮮な空気を循環させる高機能換気設備は非常に有効です。
また、患者や高齢者は寒暖差に弱いため、熱交換機能付きの換気設備は室温を安定させる上でも重宝されます。
さらに、におい対策や空気のよどみ解消にも大きく貢献します。
高機能換気設備は非常に有用なシステムですが、設置前には必ず確認すべき具体的な条件があります。
ここでは、施工面や運用面で注意したいポイントを3つに分けて解説します。
高機能換気設備の導入には、一般的な換気扇と異なり、配管・電源・本体設置の3要素が必要になります。
そのため、以下のような工事が発生します。
工期は建物の構造や設置台数にもよりますが、住宅で1〜2日、法人施設で3〜7日程度が目安です。
とくに天井裏にダクトを通す場合や、防音・防火処理を要する施設では、追加の日数と費用が発生します。
設計段階から業者と緊密に打ち合わせを行い、事前に見積とスケジュールを把握することが重要です。
高機能換気設備は24時間稼働が前提であるため、月々の電気代も気になるポイントです。
ただし、一般的な住宅用モデル(消費電力20W前後)であれば、1か月の電気代は約100〜300円程度に抑えられます。
加えて、機種によっては「自動モード」や「間欠運転」機能を使うことで、さらに省エネ運用が可能です。
初期投資は高めでも、ランニングコストを長期的に抑えられるという点で、コストパフォーマンスに優れています。
また、半年に1回程度のフィルター交換(数千円)は想定しておきましょう。
法人施設の場合は、保守契約によって定期メンテナンスを委託するケースも多く、予算化が必要です。
高機能換気設備の寿命は、機種と使用環境によって異なりますが、一般的には10〜15年程度が目安とされています。
この期間を最大限に活用するためには、以下のようなメンテナンスが推奨されます。
。
また、設置から10年以上経過した機器については、異音・異臭・風量低下などの兆候を見逃さないよう注意が必要です。
耐用年数の確認と更新時期に合わせた機種の再選定を定期的に行うことが、快適な空気環境を維持するためのコツとなります。
高機能換気設備は、従来の換気システムと比べて「空気の質」「省エネ性」「快適性」を格段に高めることができる次世代の設備です。
特に全熱交換器を搭載した機種は、温度・湿度・空気清浄を同時に行うことができ、住宅・オフィス・医療施設などさまざまな空間に適しています。
とはいえ、初期投資が高く施工も専門的であるため、導入前には設置条件や法令要件、運用コストなどを十分に検討する必要があります。
また、製品の性能差や設置後の維持管理に関する知識を持つことで、後悔のない選定と運用が可能になります。
快適で安心な空気環境を実現するためには、「何を選ぶか」だけでなく、「どう使うか」も重要です。本記事を参考に、ぜひ高機能換気設備の導入をご検討ください。
ReAirでは高機能換気設備の工事はもちろん、国が推奨している換気量に合わせて一から室内の環境を設計することもできます。
換気対策で工事をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

2026.01.30
建築・建設

2026.01.28
換気設備

2026.01.23
内装デザイン